華奢なワインの瓶を大きく振り下ろして樫の机を叩く。透明な破片が蜘蛛の子を散らしたようにわっと外側へ逃げて、私の足元でばらばらになった。踏んづけたらきっと痛いのだろう。赤い血が流れるのだろう。でも夢だから痛くない。夢の中に痛みはない。
私はすでに夢と現実の境を失っていた。「目覚めている」ときは少なくとも感覚は鋭敏で、怪我をすることもあった。ワインボトルを砕いたら破片で瞼を切って大学の先生に叱られた。両目にガーゼでふたをされて、次に目が覚めたら、もう私の体はぜんぶがぜんぶ夢の淵へ転がり落ちてしまっていた。
夢に落ちた私に、現実からたくさんのひとが呼びかけているのがわかった。部屋にはたくさんの人が来る。でもそのうちの何人がほんとうに存在しているのか自信がなかったし、彼らの言葉はくぐもっていて、うまく聞き取れないことが多かった。
けれど今日の来客は少し様子が違っていた。私が割り散らしたガラスの破片を黒い靴で踏みしめながらこちらへ近寄ってきて、子供みたいなまん丸の黒い目で私をじっと見つめる。
「“白昼夢”というのは、お前のことだな」
さあ。私は首を傾げて、瓶の首のところを口元に当てる。唇が裂けてたちまち手元が真っ赤に染まる。こぼれた雫はたぶん、赤いバーベナに変わる。
ぼろぼろと落ちていく崩れた花で、私の足元はすぐにいっぱいになった。唇の血はもうない。握りしめていた瓶の首は紫色のカトレアの花束に変わる。目の前の黒い目の男は私の手元を興味深そうに眺めながら、何か分厚い本のようなものを左手の上に“つくった"。
「あなたも夢みたいなことするんだ」
そう言うと、彼は僅かに微笑んで一歩こちらへ踏み出してくる。黒い目。黒い髪。黒い服。額の十字架。
「クロロ」
名前を呼ぶと、彼は驚いたように私を見た。私は微笑んで、長い息を吐いた。
足元の赤い花はゆるやかに伸びてリコリスになる。一面真っ赤な部屋に、彼と私だけが立っている。樫の机は粗末な墓石になる。
クロロがそこに刻まれた名前を静かに読み上げた。耳慣れた音のような気がしたけれど、それが誰なのか、私にはもう思い出せなかった。
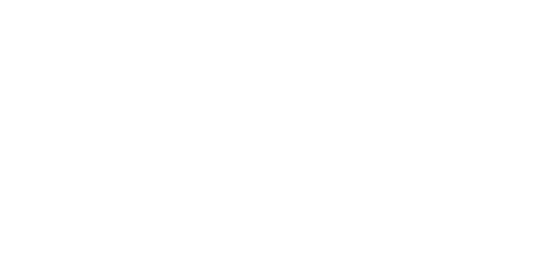
|