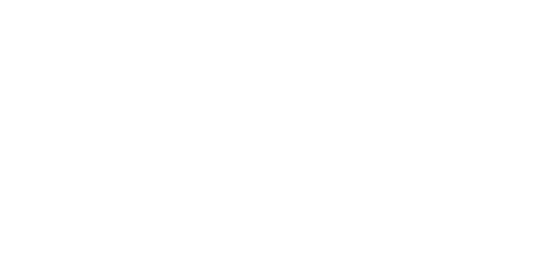次々積まれていく色々な本を空っぽの棚に順序良く並べていくように、私はじっと先生の話を聞いた。先生は白衣の裾をいじりながら、よれたスラックスのしわの通りに足を組む。青い窓の外で小鳥がさえずっている。私は先生の顔を見ずに頷いて、小さくお礼を言った。日差しが暖かい。褪せた緑色のスリッパに突っ込んだつま先だけがじんじんと冷えている。
先生が立ち上がって、誰かを呼んだ。訛っていて聞き取れなかったのか私の頭がついていけなかったのか、よくわからないでぼうっと座っていると、看護師さんがやってきて私の腕を引っ張った。私は二、三歩ふらついてから、紐をつけられた犬のように白い服を追いかける。
薄暗い病院のなかには冷たい空気が入り込んでいた。木々が枯れ、空気が凍る季節がすぐそばまで来ている。明日からはきっと、もっと暖かい場所で夢を見られる。
* * *
私は最初にペンキを要求し、部屋の壁と天井と床をすべて薄紫色に塗った。目覚めの時間の色だ。眠りたくはなかった。
行くべきあてのない私は長く病院の一室で保護され、その間何度も夢を見た。真昼にまどろんでそうなることもあれば、夜のうちに見ることもあったし、目が覚めたつもりでまだ体半分そちらにおいていることもあった。
目覚めていても、私はもはや自分が誰だか思い出すことすらままならなかった。あるいはどこかで落としていたのかもしれないが、どこで落としたのかもうわからないし、もしかして目覚めているつもりでずっと夢を見ているのではないかとも考えたが、目を覚ます方法はわからなかった。
私の見る夢は、夢らしい夢でいて、それでも確実に私の実在を脅かしている。けれど、そうだ。夢なんかで脅かされる実在なんてものは、ほんとうは実在していないという証ではないのだろうか。もっとも、私には何かを確かめる術などないのだが。
白い布と綿と銀色の糸でいくつもクッションをつくって、雲のかわりに床に敷き詰めた。朝日のかわりに白いランプを部屋の隅において、その上あたりの壁に白いだるまピンをさした。
私は満足して、背中から倒れる。執拗にしきつめた雲をつきぬけて、わたしは空へ落ちていく。
* * *
「空から人がふってくるなんておとぎ話だけだと思った?」
テーブルをはさんで向かいからこちらをじっと見ている青年に、私はできる限り人のよさそうな笑みを返した。彼は何も言わずに、真っ黒い目をちらちらと瞬かせる。まだ低い朝日が真横からさしてきて、鼻筋に長いまつげの影が落ちていた。
「今もわりと、夢でも見てるんじゃないかって気分だな」
「夢だよ。これは夢」
コーヒーにミルクと砂糖を足して、細いスプーンでくるくるかきまぜる。テーブルの上を舞うほこりが私が手を動かすたびきらきらして、なにかの魔法みたいだ。クロロは私の言葉を聞いているのかいないのか、自分のコーヒーを飲みながら、どこか遠くを見るような目をしている。視線の先をたどってみると、壊れているのかノイズのひどいテレビがあった。音は聞こえない。
「さっきは受け止めてくれてありがとう。実は死ぬとどうなるか、まだよくわからないの」
甘いコーヒーに口をつけて、またどこか別のところを見ているクロロにそう言う。彼は困ったように肩をすくめた。
「おかしなことを言うね」
「あなたも十分変。前に会ったときとぜんぜん違うもの」
「前に?」
黒い目がふたつ、また私をまっすぐにとらえる。私はスプーンの柄に細長く写る私をちらりと見て、それから慎重にクロロの瞳の中を覗いた。
「私もぜんぜん違うみたい」
目の前がちかちかする。光るほこりが私の周りで渦を巻く。綿の中にうずもれていく。宙に投げ出されたように感覚のなかった体がじわじわと重くなっていく。誰かが受け止めてくれた背中の感覚は、やがてやわらかい枕に変わった。