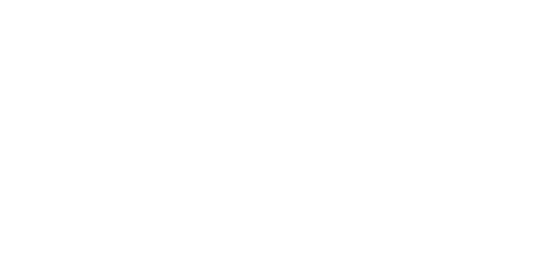さっきまでは目が覚めていたような気がする。不確かな感覚を信じるなら、あれは現実で、これは夢だ。安っぽい小さなくまでとシャベルが入ったバケツを足先でつつくと、輪郭のぼやけた子供がどこからか立ち上がり、じりじり音を立てて消えた。広い砂場は沈黙する。
この夢が長いのか、あるいは短く途切れながら続いているのか、私にはわからない。記憶は私の企んだとおりに消えてしまってここに無い。もっと思慮深く生きるべきだったと後悔しても遅く、私に残されたのは砂を踏む足と、行き先の自由だけだった。
公園に来ようと思ったのは単なる思い付きで、そこに何もないことはわかっていた。近所で一番大きくていつもにぎわっていた公園。抹消されずに残っていた断片から組み立てた、何の意味もない記憶の具現化だ。
無意味と思えばそこから瓦解する。私は目を閉じて流砂に身を任せる。目を開けるとそこには何もない。思わなければ何もない。ここはきっと、私の頭の中だ。
* * *
ふと気付くと私はベッドの上にいた。周囲は暗く、非常灯らしい緑の灯りがまだらに汚れた薄いカーテンごしに目を刺す。自宅、ではない。学校の保健室、でもない。病院、そう、たぶんそれだ。
私は躊躇いなく布団を払い除けて、カーテンを開けた。ひととおりの設備が揃った個室だったが、狭くてなんとなく不衛生だった。ベッドの下には埃が積もっていて、よれよれのスリッパと薄汚れたサンダルが一足ずつ揃えてある。私はサンダルをつっかけて、ドアのない病室を出た。
廊下は非常灯がついているだけで、ひやりとするほど暗い。先の見えない曲がり角の奥から得体の知れない何かが出てくる想像をしながら、私は一歩ずつ後ろへ下がった。私の病室は角部屋で、すぐそこにはつきあたりがあるのを横目で見ていたからだ。
背中は思ったとおりにひやりとした壁の感触をつかんだ。左手に病室、右手には階段があり、そこはなんとなく明るい。踏み外さないように考慮されているのだろう。踊り場はやけに広くなっていて、座り心地の悪そうな四角いソファとがたがたのテーブルと、真っ暗の自動販売機がある。かと思えば唐突にオレンジ色の光がぷつんぷつんと弾けた。管理されていない、おそろしい自動販売機。これこそ得体の知れない何かであろう。
吸い込まれるように踊り場を通り抜け、階段を下っていく。この先には、たぶん、外に出られるところがあるに違いない。目を上げると壁に1分の2と書いてあって、すぐ下が地上であることは容易に想像がついた。
廊下をでたらめに抜けて、中庭の見えるところにさしかかると、不意に風が吹きぬけていくのを感じた。
管理の甘い病院だ。ナースセンターの蓮向かいなのに視線の一つも感じないし、いくらでも死ねそうな木や鋭いオブジェがおおらかに配置された庭へは、ほんのドア一枚しかない。それも当然のように開け放たれていた。
私は迷いなく外へ出て、柴の匂いをいっぱいに吸い込む。湿った木のベンチの上には枯葉が積もっていて、見ればあちこちが土に汚れている。誰もここで深呼吸などしていないのだろう。草と土のにおいなのに、病院特有のやつれたにおいが風に渦巻いていた。私はそっとベンチに体を横たえる。
鼻の奥に砂のにおいが残っている。砂ににおいがあるのかどうか、本当のところはわからない。けれど私はそれを砂のにおいと呼ぶほかに表現しようがなかった。そしてふっと、なぜそんなものを抱えているのだろうと首を捻る。大方夢でも見ていたのだろう。
箱型の病棟はまるで隔離施設のようだった。渦巻くやつれた風が、痛みに呻く声をつれてくるような気がする。けれど私はそんなおそろしい想像をすりぬけて、穏やかに、ゆっくりと、眠りへ身を沈めていった。
* * *
冷たい煉瓦の床の上でうつぶせになっていた私は、こちらを静かに見下ろしている男に微笑んだ。生きていますよ、問題ありません。その意図を読み取ったのか、彼はふっと身を屈めて私の顔を覗き込む。
「いつからそこに居た?」
「ずっと前から?でもたぶん、今もここにはいない」
寝返りをうって死人のように横たわり、深く息をする。砂の匂いは消えない。金の燭台があちこちで爛々と輝いている。炎の暖かさは感じない。冷ややかな砂が私をとらえている。私とは一体誰のことだったろう。
一息に体を起こして、薄暗くて息の詰まりそうな部屋を見回す。男は私の左手側にいて、片膝をついて座った姿勢で、やはり私をじっと見ていた。観察する眼。暗がりでも、整った幼げな顔立ちと前髪の向こうの十字架はよく見えた。
「意味を掴みかねるな」
「ごめんね、私もよくわからないんだ」
立ち上がって彼を見下ろす。艶のある黒髪が揺らぐ火に輝いている。私はふと自分の手足を見下ろし、眩暈を感じた。私とは、いったい?この体は、だれの?
「ねえ、名前を教えて」
気付いたらそう口走っていた。俄に崩れ出した"わたし"の虚像を繋ぎとめる唯一の糸口がそこにあるとでもいうように、私は真剣だった。それでもどこか浮ついた感覚が体中を支配している。サンダルで踏んでいるはずの床は、崩れていく流砂のように覚束無い。
「……クロロ=ルシルフル」
「ありがとう。覚えるね。私のことは、忘れていいよ」
崩れていく。クロロの暗い目が私を追う。彼の目に私がどう映っていたのか、それを知ることさえできれば、私はなにかを取り戻せるのだと思った。ただ私は、その思いすら留めておくことはできなかった。
砂の上に戻される。私はまた空っぽになって、呆然と座り込んだ。