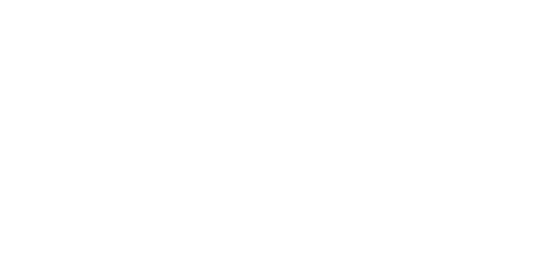足元には砂があって、私の素足が半ば埋まっている。昨日足の甲に沸騰した味噌汁を鍋ごと落とした記憶があったが、痛みも火傷も痣も傷もない。それもそのはず。あれが夢で、これが夢。見上げれば安っぽい紺色の天井にレモンがぶら下がっていて、雲のかわりに蚊取り線香の煙が揺蕩っていた。
いつまで待っても目が覚めない。夢を見ていることはわかっているのに、確かな記憶を置いてきた、あの現実にはどうやっても帰れない。
夢の中では、私は必ずしも私ではない。あるときは絶世の美女であり、あるときは冴えないサラリーマンであり、あるときは希望に胸を躍らせる若い学生であり、そしてときどき思い出したように私に戻る。
でもその私は、私と呼ぶにはあまりにも私を欠き過ぎていた。
名前も年齢も住所も職業も親類関係も恋人の有無もわからない。姿形から、普通の女であることだけはわかった。でもあまりにも普通の女なので、私はそいつがどういう人間なのか推理できない。
それでもその姿をとっているとき、私は私が私であることを認識できる。そのときに限って、私は夢の中を自由に歩くことができた。
* * *
砂浜を踏みしめると、小さな蟹が足の上を慌てて走り抜けていった。見上げれば上弦の月がおぼろげに光っている。しっとりとした濡羽色の空には宝石を散らしたように星が瞬いて、水平線の奥には対岸の街の灯が夢のようにきらめいていた。言葉のあやは置いておく。
「きれいですねー」
波打ち際から躊躇いなく海に入って呟くと、背後で男が笑った。人の気配のような何かがあることはずっと前からわかっていて、私はたぶん、狙ってそこに落ちてきたのだ。前後関係も横の連なりも曖昧でわからないけれど、私の意志でここに来たことだけは確かだった。誰か話を聞いてくれそうな人を探していたのだ。
「……ああ、人間か。幽霊か何かかと思った」
水の中で舞い散る砂の感触を足に、確かめるように振り返れば、そこには黒髪の男がいる。整った顔に、崩れたオールバックと長いコート。額には十字架の刺青。変な人だ、と私は呟いて、そのまま海の深いところに背中から落ちた。水が冷たいのがはっきりとわかる。自分があることが嬉しくて笑えば、男は怪訝そうな顔で私にじっと視線を送る。
「何をしてる?」
「さあ。終わりを探してる?」
「終わり?」
「夢の」
淡々と答えて月を見る。こんなに良い夜なら満月が見たかったような気もするけれど、レモンしかなかったから仕方がない。絵の具の匂いがする。
「ずっと夢を見てるんだ。どこで始まったかは思い出せるけど、どこで終わるのかわからないの」
「お前は何だ?」
人の話を聞かない男だったか。それとも聞いているだけで相槌を打つとかキャッチボールをする気遣いがある男ではなかったか。私は答えずに冷たい海に潜って、砂の中からサンダルを拾った。乾いた感触がする。
「さようならだね、クロロ」
「なぜ俺の名前を知っている?」
「さあ。会ったことあるんじゃない?」
顔だけ出してそう言って、私はそのままぶくぶくと消えた。波の音は雨の音に変わる。窓の外が明るくなっている。
砂を撒いた床には蟹の死骸が転がっていた。