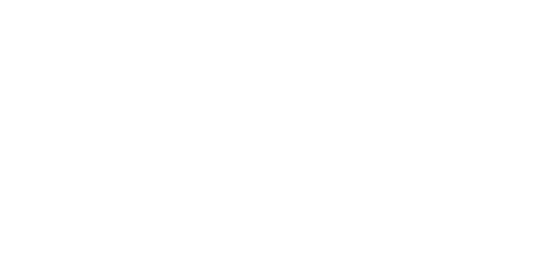出かけた先は最寄のコンビニだった。日曜の午後の朗らかな陽気にうんざりしながら、だらだらと立ち読みをして、棚を隅から隅まで点検して、60円ちょっと使って出てきた。アイスが美味しくて少し気が持ち直したかと思えば、急に薄ら寒くなってくしゃみがでた。つまり、あまりよくない気分だった。
その気分のせいか、はたまた来るべき平日への計り知れない絶望がそうしたのか。ほんの数十メートル、通い慣れた一本道で、私は一瞬世界がぐるりと回ったのを感じた。平行に、きっかり90度ずつ。目の前の直線道路が私の左右にも同じように伸び、振り返ってみると後ろの道も前方と同じ風景に変わっていた。
その時点ではまだ何もおかしいとは思っていなかった。私は立ち止まって冷静に棒アイスを舐め尽くし、まっさらな棒に溜息をついた。当たりつきという謳い文句のわりに、私はその当たりを引いたことがない。
そして悪気なく、その棒をアスファルトの上に落とした。棒の先は右の道を指し、それを皮切りに前後と左の道は煙のように消えた。このあたりでまた薄ら寒くなって、洟をすすりながら振り返ってみると、そこにはもう何もなかった。いや、語弊である。砂漠があった。
自分が白昼夢に囚われたことに気付くまで、実際かなりの時間を要したように思う。そもそも夢というものは、思考がやたらと停滞したり、かと思えば急に加速がついてわけのわからない結論に至ったりするものだ。
とにかく、私はそこに十分な時間立ち尽くしていた。それからようやく何かしなければならないと思い至り、砂に呑まれたサンダルを脱いで砂山をよじ登ると、遠くに町のようなものが見えた。しかしそれが蜃気楼であることを私はわかっている。空腹もなく、照り付ける太陽の光も疎ましくなく、裸足は焼けた砂ではなく、何かひんやりとしたものを掴んでいるような気がしている。
これは夢だ。
確信を持ってそう呟けば、今度は視界が垂直に回転する。私の体はその動きに合わせて大きく弧を描く。投げ出されたと感じて反射的に目を瞑ってしまったので、風景がどんな風に変わっていったのかは知らない。居眠りをして、ふいに身体ががくりと落ちたときのような感覚がした。夢が夢だと自覚すると、たいていそれは覚めてしまう。明晰夢を見るたちではないから、きっとこれで目が覚めるのだろう。
そう思いながら目を開けると、私は見知らぬ街の中にいた。
「……いま、起きたよね?」
呟きは私の意図するとおりに口から流れている。手足の感覚は鋭い。嗅いだことのないにおいがする。寝起きのように瞼が重い。試しに頬をつねってみると、狙ったとおりのやわらかい痛みがじわじわと神経を登ってきた。
私は首を傾げ、人の流れのないところに移って持ち物を確認した。充電切れの携帯、残高千数百円の財布、鍵、アイスの袋とレジ袋。さっき夢の中で脱いだと思ったサンダルはしっかりと足についていたが、道に捨てたアイスの棒はなくなっていた。
何か大変なことが起こっているのかもしれない。私はそう考えながらも、信じきれずにただ黙って座っていた。
お金は減っていない。夢うつつのまま歩いてきてしまったとしてもこんな街にたどり着くはずがない。聞こえる言葉は日本語のようだったが、ただの迷子だと安心することはできなかった。決定的に何かが違う。まだなんとなくぼんやりしてうまく働かない頭が、私に何か警告をしていた。
動くべきか、動かざるべきか。それが問題だ。私はそれらしく口許に手をやって唸り、そして程なくして諦めた。こういう自分の度量を超えた問題が発生した場合、慌てふためいたり安易な解決方法を求めるのは愚行である。実際にはかなり慌てていたし、歩き回って何か理由を見つけて自分を安心させたい気持ちはあったが、そういうことをしてどうにかなる状況ではないことを指し示す証拠を、私は見つけてしまったのだ。
遥か空、奇妙な顔の模様がついた飛行船。そしてその腹に書かれた、どこかで見たことのある記号。ずるずる引き下げた視線でとらえた、ありふれた店先にある、あるはずのない文字列。
「……うわあ!」
私は努めて明るくリアクションし、そして意識を失った。
* * *
眠ったらなんとかなる。これは白昼夢だ。目が覚めたらなんとかなる。ただの明晰夢だ。
私はずいぶん前に目が覚めているのに、目を閉じたまま、薬のにおいがする布団に潜ってじっと息を潜めていた。さっきから廊下で珍奇な名前が呼ばれている。それは絶対日本語じゃない。でも文法からしてどう考えても日本語だったので、私はことさらに打ちひしがれたような気持ちになった。
自分の状態をどう表現したら的確なのか、私はよく知らない。とにかくとんでもなく奇妙で、とんでもなく理不尽で、そしてどうしようもなくお腹が空いている。これはどう考えても一夜を明かした胃袋だ。こんな時まで正常にエネルギーを吸収しなくてもいいのに、持ち主に似て律儀な臓器だ。
そこまで考えたところで、私はようやく布団を顔の上から退けた。そしてすぐに戻し、また退ける。それを何度か繰り返していたら看護師のおばさんがばたばたとやってきて、ひどく訛った言葉で「ああよかった目が覚めたんですね、今先生を呼んで来ますから安静にしていてくださいね」と言った。もっとも、私がそれを全て理解したのは実際に先生が来た後だったが。
「よかったよかった、安定したのに全然目を覚まさないもんだから、こんな小さな病院じゃどうにもならない病気なのかと思ってドキドキしてたんだよ」
先生は、人好きのする笑みの、ちょうど私の両親くらいの歳の男性だった。私は「はあ」とか「へえ」とか言いながら、半ば上の空でその話を聞く。
どうやら私はキャパシティオーバーで脳みそを強制終了したあと、善意の市民の通報を受けてこの病院に搬送されたらしい。今は全く以って良好だが、一時呼吸や心臓が止まっていたのだそうだ。しかし先生は「あー止まったねーダメかもねー」と見ていただけで特に処置をしていないというので、私はかえって安心した。お金がないので治療費と言われても夜逃げするしかない。ベッド代だけでも親に頼るのが怖いくらいだ。連絡先を聞かれたら覚えていないふりをしよう。
「それで君、名前は?」
「はい?」
「いや、持ち物見ても身元がわからなくてね。まだご家族に伝えられてないんだよ。心配してると思うよ。連絡先とか覚えてる?」
私は、ぽかんとした顔で先生を見た。先生は笑顔をやめて、おや、という顔を作る。
「あれ、君……」
「……あれ?」
先生の顔を見上げながら、私は内臓が縮み上がるのを感じた。
いまわたしは、記憶喪失のフリをしようとした。フリだけだ。自分がどこから来て、何者で、家族がどんな人間で、預金口座にいくら入っているかもわかっていて、だからそうしようとした。そのはずだった。
私は呆気にとられて黙り込んだまま、先生の気の毒そうな表情を眺める。空っぽになった頭の中で、不安だけが渦巻いていた。